政治と医療は、決して無関係ではありません。医療制度は国民の生命・生活に直結する以上、政治の意思決定がその根幹を左右します。
参政党は、「自然」「自己責任」「真実」といった一見もっともらしい言葉を掲げながら、医療に対して非科学的な懐疑や極端な自己責任論を展開してきました。
私は町医者の一人として、そして社会保障制度の恩恵を受ける市民の一人として、彼らの主張には看過できない危うさを感じています。
参政党が提示する医療・福祉政策のうち、特に問題のある三点を取り上げ、それぞれについて医学的観点から反論を試みます。
ワクチン忌避思想と「自然免疫万能論」
参政党のウェブサイト(https://sanseito.jp/2020/news/5105/?utm_source=chatgpt.com)を見ると
- mRNAワクチン接種による自然免疫力の低下
- 自然免疫力の低下(新型コロナのみならず様々な感染症に罹患しやすくなり、がんを誘発する等)」
- 血栓症や免疫異常、自己免疫疾患リスク
- 血栓症及びこれが誘発する様々な疾患
- 反復接種による自己免疫疾患の誘発
- 卵巣への集積による月経異常や不妊症など
- 「頻回接種は危険」「用心すべき」との姿勢
- 「頻回接種が危険であることは教科書的事実」
- 「接種回数を重ねるほど副作用・後遺症発現のリスクが高まる」
が主張として掲載されています。
❗ 医師からの反論
現時点で、参政党が根拠とする「自然免疫低下」や「ガンや不妊への誘発」などを裏付ける、査読付きの一次論文や大規模疫学研究は確認されていません。
- 一部の研究では「心筋炎」などの極めて稀な副反応の可能性が指摘されていますが、ガン・不妊・自己免疫疾患との因果関係は未確定で、参政党が言うような「明確な因果」や「頻回接種でリスク激増」まで示すデータは見られません。
- 国際的な公衆衛生機関(WHO、CDC、EMA など)は、mRNAワクチンの総合的な利益が副反応リスクを上回るとの結論で、特に小児・高リスク群に対してはワクチン推奨を続けています。
医療費削減の名の「医療依存」否定
参政党公式サイト(https://sanseito.jp/political_measures_2025/specific_policies/?utm_source=chatgpt.com)における 「健康・医療」 セクションでは、以下の文言が掲載されています
- 「対症医療から予防医療に転換し、無駄な医療費の削減と健康寿命の延伸を実現」
- 「予防医療を積極的に健康保険の対象にし、診療報酬額を高く設定」
- 「かかりつけ医制度を原則化し、医師への診療報酬は担当する人数に応じた定額制とし、治療や投薬はその定額費用の範囲で賄う制度を導入」
- 「薬局で購入可能なOTC医薬品で対応可能な疾病は、原則処方しない」
つまり、参政党の主張の方向性を要約すれば、以下のような考え方に基づいていると読み取れます
- 「病気にならない生活を送れば医者はいらない」
- 「OTC(市販薬)で対応できる病気には、医者が関与すべきでない」
- 「安易な受診を控え、高齢者の来院を2割減らせば5兆円規模の医療費削減になる」
ということになります。
❗ 医師からの反論
この主張は、健康を自己責任に帰しすぎる危険な思想です。確かに予防や生活習慣の改善は重要ですが、それですべての病気を防げるわけではありません。
1. 「医者はいらない社会」は幻想である
たしかに予防医療の推進は重要であり、生活習慣病の予防や健康教育の充実は歓迎されるべきです。しかし、それと「医療機関を利用しない社会」を結びつけるのは論理の飛躍です。
病気は不注意の結果だけでなく、加齢・遺伝・環境要因など不可避のリスクによっても発症します。いくら健康的な生活を心がけても、がん・脳卒中・心筋梗塞・自己免疫疾患などは誰にでも起こり得ます。
また、高血圧や糖尿病といった慢性疾患は初期に自覚症状が乏しく、早期発見には医療機関での定期的な診察や検査が必要です。
現実には「予防=医療不要」ではなく、「予防+医療の適切な組み合わせ」でしか健康長寿は実現できません。
たとえば高血圧や糖尿病は「沈黙の疾患」とも呼ばれ、症状がないまま進行し、脳卒中や心不全といった致命的合併症を引き起こします。
また、がん検診やワクチン接種など、公衆衛生的な介入こそが重症化・医療費増大を防いでいます。
2. OTC(市販薬)だけでは医療の質は保てない
OTC薬は軽度の症状に対しては有用ですが、その適応範囲は限定的です。医師による診断なしにOTC薬を乱用した結果、症状を見逃して重症化した事例は数多く報告されています。
- 胃もたれと思って市販の胃薬で済ませていたら、実は胃がんの進行期だった
- 頭痛薬を常用していたら、脳腫瘍や慢性硬膜下血腫だった
- 喉の痛みに風邪薬を使っていたが、扁桃周囲膿瘍や急性白血病だった
たとえばフランスの大規模コホート研究では、NSAID使用が扁桃周囲膿瘍リスクを約3倍に増加と報じています(PMID: 30423110)。また白血病に関しても3歳男児が4か月間、繰り返す微熱と関節痛を風邪だと思って市販薬を服用していたところ、急性リンパ性白血病と診断された症例が報告されています(PMID: 37625122)。このような大規模コホート研究や症例報告は医学専門誌に多数掲載されいるのです。
こうしたケースは現場の医師には珍しくありません。自然療法についても、効果の科学的根拠が乏しい手法が含まれることがあり、過信すれば診断の遅れや重症化を招く可能性があります。
3. 「医療費削減ありき」は、結果的に高コストになる
参政党は「高齢者の受診を2割減らせば5兆円削減できる」としますが、これは非常に短絡的な経済観に基づいています。
高齢者の受診を抑制すれば、一時的には医療費が下がるかもしれません。しかし、早期発見・早期治療の機会を逃せば、症状が進行して入院や手術・介護が必要になるリスクが高まります。結果的には、医療・介護を合わせた社会保障費全体が増加する可能性があります。
※OECDの医療支出分析では、「一次医療(初期診療)を抑えすぎた国は、むしろ総医療費が高くなる傾向」があることが指摘されています(https://www.oecd.org/en/publications/2023/11/health-at-a-glance-2023_e04f8239/full-report/health-expenditure-on-primary-healthcare_bf72cd24.html?utm_source=chatgpt.com)。
また、「来院2割減」の具体的なシミュレーション根拠は示されておらず、政策としての再現性や倫理的妥当性にも疑問が残ります。
さらに、高齢者や多疾患患者が自己判断で薬を購入・使用することで、薬剤相互作用や副作用のリスクも高まります。医師の判断を介さない医療は、むしろ医療の質と安全性を損ないます。
市販薬と自然療法中心の制度では、こうした「沈黙するリスク」を見逃し、結果的に重症者を増やしかねません。
「病院にかからない社会」は理想に見えて、実は健康格差を拡大させる可能性があります。
終末期医療の「全額自己負担」政策
参政党の主張として
- 「90代の延命治療に保険は不要」
- 終末期医療は本人または家族の負担でまかなうべき
前掲の参政党の公式ウェブサイト「政策2025」では、以下のように明記されています:
終末期の点滴や人工呼吸器管理等延命治療が保険点数化されている診療報酬制度の見直し
終末期の延命措置医療費の全額自己負担化
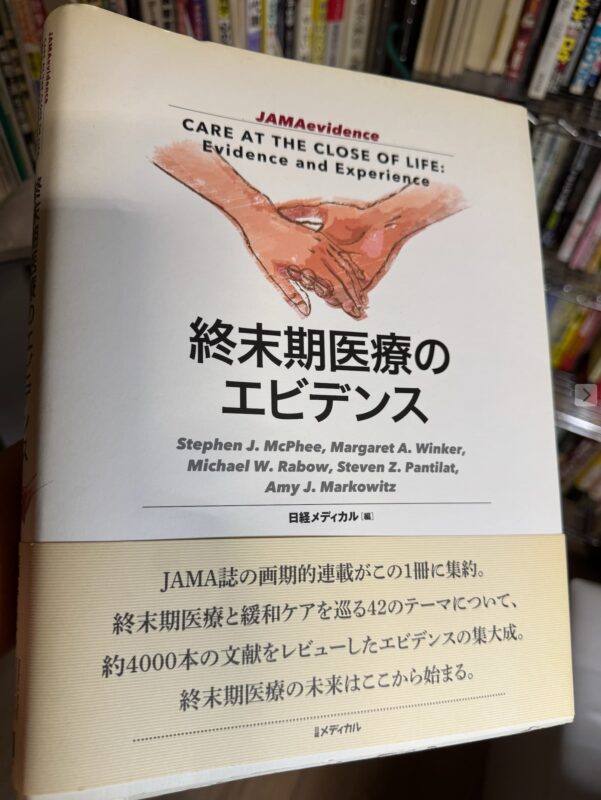
せめてこのレベルの本を一冊は読んでから発言していただきたい。
※本稿では、厚労省や医療現場で用いられている「終末期医療」=緩和ケア・心理支援を含む包括的医療として用いています。参政党の用語(「終末期延命措置」)とは意味が異なるため、以下ではこの違いを踏まえて議論を展開します。
以下では、この用語の違いと現場での実情を踏まえて、参政党の政策提案を検討していきます。
❗ 医師からの反論
この発想は、終末期医療を「無意味な延命」と誤認している点で危険です。
現在の緩和ケアは、むしろ「延命ではなく、苦痛を取り除き、穏やかに人生を終える」ための医療です。点滴や酸素だけでなく、心のケアや家族の支援まで含む包括的なケアが重要です。
このような医療を「自己負担」にすることは、金銭的理由で“穏やかな最期”を諦める人を生む社会につながりかねません。
1. 「延命治療=無駄」という認識は誤り
参政党の主張は、あたかも終末期医療=無意味な延命という前提に立っていますが、これは現代の終末期医療の実態を大きく誤解したものです。
現在の終末期医療(特に緩和ケア)は、単に命を引き延ばすことが目的ではありません。
むしろ以下のような人間の尊厳を支える医療です:
- 身体的苦痛(痛み・息苦しさ・吐き気など)の緩和
- 不安や孤独への心理的支援
- 家族との時間を大切にするための環境整備
- 自宅やホスピスで最期を迎えたいという希望の実現
終末期医療=チューブだらけの延命ではなく、「苦しまず、穏やかに逝くための医療」です。
2. 「90代の命に価値がない」と言っているに等しい
「90代の延命に保険は不要」という発言は、“ある年齢を超えたら社会的に支える価値がない”という思想に基づいています。
これは、次のような人々を「不要」と暗に宣言しているに等しいのです:
- 長年社会に貢献してきた高齢者
- 病気を抱えていても意志を持って生きている人
- 老老介護の末、ようやく緩和医療にたどり着いた人
命に「社会的価値」を持ち出す発想は、医療の倫理のみならず、人権思想や憲法の理念とも相容れません。
3. 「自己負担化」は、経済力による“死に方格差”を生む
終末期医療を全額自己負担にすれば、次のような状況が現実に起きます:
- お金がないから、痛み止めを打たずに逝くしかない
- 「家族に迷惑をかけたくない」と苦しみながら死を受け入れる高齢者
- 在宅緩和ケアやホスピスが選択肢から消える
これはまさに、「経済的に余裕がある人だけが、穏やかな最期を選べる社会」です。
厚労省の調査でも、緩和ケアにアクセスできるかどうかは「医療費負担意識」と強く関連していることが示されています。
4. 終末期医療は「家族の医療」でもある
終末期の医療は患者本人だけでなく、家族の心理的・社会的ケアにも直結します。
たとえば、
- 最期の時間をともに過ごす準備
- 不安・後悔・介護疲れの軽減
- グリーフケア(死別後のサポート)
これらがなければ、「もっと何かできたのでは」と家族が長年苦しむことになります。
それは本人の死に対する“意味づけ”さえも崩してしまうでしょう。
※なお、参政党は「終末期延命措置」の自己負担化を主張していますが、「終末期医療」全体を指しているかのような見出しも出回っており、報道・受け取り手双方に誤解が生じています。本稿ではその区別を意識しつつ、医療の現場での実際や影響を論じています。
【結論】科学と人権のバランスを見失わないために
参政党の医療政策は、表向きは「健康自立」や「自然との調和」をうたいながら、その内実は科学的根拠の軽視と、公的医療制度の切り縮めです。
「医療費の抑制」や「命の選別」といった発想は、経済合理性を追求するあまり、弱者や高齢者を社会から排除しかねません。
私は一人の医師であると同時に、年を重ね、やがて誰かのケアを受ける側になる市民でもあります。
その立場からも、「自己責任」の名のもとに医療や福祉の基本的人権を切り捨てるような政治には、声を上げなければならないと考えています。
科学に耳を傾け、人の尊厳を守る。
そんな当たり前の社会の軸が、揺らいでしまわないように。
